仮想通貨関連資格はなぜ「意味がない」と言われるのか
業界での資格の認知度・信頼性
仮想通貨・ブロックチェーンに関する資格は、現状では業界内での認知度が低く、企業や専門家から高く評価されにくいのが実情です。
実際、転職サイトの求人情報を調べても、これらの資格を採用条件に明記している企業はほとんど見当たりません。
日本国内で唯一の専門資格とされる「暗号通貨技能検定」ですら、企業側の認知が十分でないため、取得しても直接的な評価につながりにくい状況です。
また、海外発の資格(例:米国Blockchain CouncilによるCertified Blockchain Expertなど)は日本では知名度が低く、採用担当者がその存在を知らなければアピール効果は限定的です。
要するに、多くの企業は仮想通貨関連の資格よりも実務能力や経験を重視する傾向にあり、資格自体の信頼性・権威付けはまだ確立されていません。
就職やキャリアにおける有用性
就職・転職面での有用性は限定的です。
IT業界一般では資格より実績を重視する傾向が強く、ブロックチェーン分野も例外ではありません。
企業はまず応募者の開発プロジェクト経験やスキルセットを見ます。
仮に資格を持っていても、実務経験が全くなければ高く評価されにくいのが現状です。
実際、「暗号通貨技能検定」を取得しただけで転職活動が有利になるとは言い切れない、とする指摘もあります。
ただし、資格が全く無意味かというとそうではなく、自身の知識習得意欲を示す材料や話題にはなり得ます。
面接などで「自主的に勉強し資格を取った」ことはアピールになり、一定の知識がある証明にはなるでしょう。
また、日本では一般的に資格保有を評価する文化もあり、社内外の初対面の相手に対して自分の知識レベルを客観的に示す手段として資格を活用できる場面もあります。
ただ、その効果は採用担当者やプロジェクト次第でまちまちであり、新興分野ゆえに資格自体の評価基準が定まっていないのが実情です。
総じて、仮想通貨系資格は「持っていれば多少のプラス要素」程度で、必須条件でも決定打でもないと言えます。
資格内容の実用性(知識・技術の現場適用度)
仮想通貨関連資格の試験内容は基礎知識の範囲が中心であり、現場の高度な技術力を直接証明するものではありません。
例えば「暗号通貨技能検定(初級)」ではブロックチェーンや暗号資産の仕組み・利点など初歩的内容が問われ、20分の筆記試験に合格すれば取得できる基礎レベルの資格です。
そのため、「ある程度知っている人にとっては、人脈作りや知識整理になる程度」とも言われており、完全な初心者が最初の一歩として受講する価値はあるものの、実務ですぐ役立つ専門スキルが身につくわけではないと指摘されています。
言い換えれば、この種の資格講座は 入門セミナー的な性格 が強く、内容も広く浅いため、エンジニアとして必要な深いプログラミング技術や設計力は別途習得する必要があります。
また、資格取得のための知識は独学や他の手段でも十分習得可能です。
実際、資格公式テキストや講義で学ぶ内容は、市販の書籍やオンライン情報からでも学べるケースが多く、資格講座に高額な費用を払うより、自力で勉強して同等以上の知識を身につけられるという意見もあります。
現場で本当に必要とされるのは、ブロックチェーンを用いた開発スキル(例:Solidityによるスマートコントラクト開発や分散アプリ構築)やセキュリティ知見などですが、それらは資格試験範囲外であることも多いです。
結果として、資格保有がそのまま即戦力につながるとは言い難く、実用面での価値は限定的だと見られています。
資格発行団体の信頼性・収益モデル
仮想通貨系資格を発行・運営している団体の多くは民間の一般社団法人や財団であり、国家資格や公的資格のような厳格な認定制度ではありません。
このため、団体自体の信頼性や中立性に疑問を呈する声もあります。
たとえば「日本クリプトコイン協会」が主催する暗号通貨技能検定は一般社団法人によるものですが、資格維持には年会費が必要であったり、合格者に「○○アドバイザー」という肩書きを与えて協会サイトに名前を掲載するなど、ビジネス色の強い運営がされています。
資格取得者から年会費を集めるモデルや、高額な受験料収入によって団体が成り立っているケースも指摘されています。
実際、同検定の初級講座・試験は約5万円、上級は約10万円近い受講料が設定されており、決して安くありません。
これら費用が知識の対価に見合うかについては懐疑的な見方もあり、
「資格ビジネス」に過ぎないのではないかとの批判につながっています。
さらに、過去にはブロックチェーン関連の資格試験が途中で終了してしまった例もあります。
一般財団法人BCCC(ブロックチェーン推進協会)がかつて実施していた「ブロックチェーン技能検定」は現在開催されておらず、関連書籍だけが残っている状態です。
このように、発行団体の都合やブームの変遷によって資格そのものが継続しないケースもあり、資格の永続性や担保性に不安があります。
総じて、仮想通貨系資格の発行団体は国や公的機関からのお墨付きが無い民間主体であり、営利目的の商業資格との見方が根強いです。
そのため、「その資格は本当に業界標準たり得るのか?」という信頼性の点で疑問視され、「取得しても意味がない」とする意見の一因になっています。
実務経験・ポートフォリオとの比較
実務経験やポートフォリオ(成果物)の評価と比べると、資格の評価はどうしても低くなりがちです。
エンジニア採用においては、「何のプロジェクトでどんな成果を出したか」という具体的な経験や、GitHubなどで公開されたコード・プロジェクトといったポートフォリオが重視されます。
ブロックチェーン開発の場合、自作のスマートコントラクトやdApp(分散型アプリ)の実装経験、OSSへのコントリビューションなどがあれば強力なアピール材料となります。
一方、資格は知識レベルの証明に留まり、実践能力を保証するものではないため、直接の比較では実務経験に軍配が上がります。
実際に専門サイトでも「どのようなエンジニア職でも最初に求められるのは実績」であり、資格があっても経験がなければ評価されづらいと明言されています。
特にブロックチェーンのような新技術分野では、自ら手を動かして開発した経験こそが信頼の拠り所です。
資格はあくまで「客観的な知識証明」にはなるものの、新しい資格ほど知名度が低く評価も一定しないため、実務経験の補足程度と考えるのが妥当でしょう。
極端な言い方をすれば、「資格しかない人」より「資格は無いが実務で成果を出した人」の方が企業から求められるケースが多々あります。
また、ポートフォリオの方がその人のスキルを具体的に示せるという点も見逃せません。
例えば、自分でブロックチェーンアプリを開発して公開していれば、使用した技術スタックや実装力、問題解決力が直接伝わります。
資格は合否という結果しか伝えませんが、ポートフォリオはプロセスや成果物そのものを示します。
この違いから、多くの採用担当者や現場エンジニアは「資格よりも何を作ったか」を重視しがちです。
以上の理由から、実務経験や充実したポートフォリオがある人にとって、資格の優先度は相対的に低く、「持っていれば尚可」程度の位置付けになっています。
まとめ
仮想通貨やブロックチェーンに関する資格が「意味がない」と言われる背景には、以上のような総合的な理由があります。
業界内での知名度不足により企業からの評価が限定的であること、採用やキャリア面で実務経験ほどには役立たないこと、資格試験の内容が初歩的で現場直結しにくいこと、発行団体が民間主体でビジネス色が強く信頼性に疑問があること、そして何より実務経験・成果物の方がスキル証明として重視されること――これらが重なり、仮想通貨関連の資格は「なくても困らないし大差ない」と見做されています。
もっとも、資格そのものを完全に否定する必要はなく、学習の動機づけや知識の体系的な習得手段として活用できる面もあります。
また、資格取得を通じて得た人脈やコミュニティへの参加機会が有益な場合もあるでしょう。
しかし、少なくとも2025年現在の日本においては、これら資格は実務能力の代替にはなり得ず、キャリア上の決定打にもなりにくいのが実情です。
仮想通貨業界で評価される人材になるためには、資格よりも現場で通用する開発スキルや実績作りに注力する方が近道だ、というのが多くの専門家やエンジニアの共通した見解と言えるでしょう。

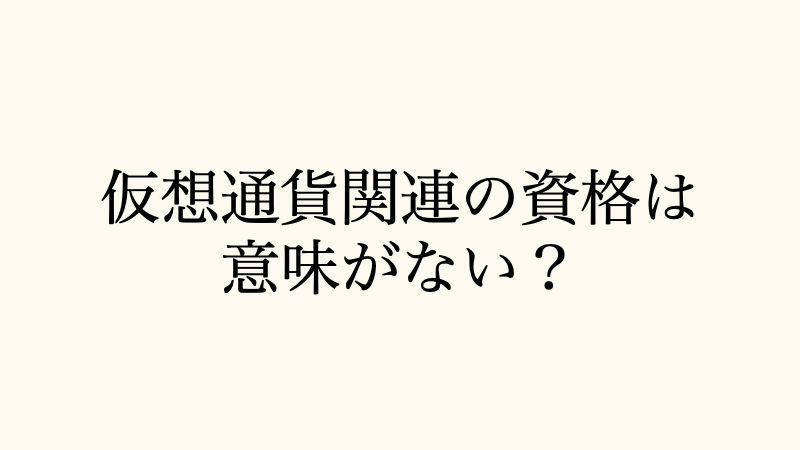
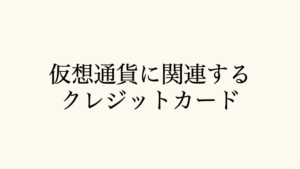
コメント