仮想通貨で支払い可能なカードとは
仮想通貨決済対応カードとは、ユーザーがビットコインなどの暗号資産を直接または間接に使って支払いができるカードのことです。
主な方式は次の3種類に大別できます :
プリペイド型: あらかじめ保有する仮想通貨をカードにチャージ(入金)し、法定通貨(円やドル)に換算して決済する方式。
事前に交換してあるため、利用時には通常のプリペイドカードの残高から引き落とされます。
例)bitFlyer VISAプリペイドカード(ビットフライヤー)では、ビットコインを円建て残高にチャージしてVisa加盟店で利用できます。
入会金・年会費無料で、スマホアプリから即時チャージできる手軽さが特徴です。
自動換算型(デビット型): カードに直接仮想通貨残高を紐づけ、支払い時にリアルタイムで仮想通貨を売却・法定通貨に変換する方式。
ユーザーは取引所口座やウォレット内の暗号資産をそのまま決済に充当できます。
例えば、Binance Visaカード(バイナンス)は取引所口座の残高から決済額相当の暗号資産が即時に売却されて支払われます。
カード利用に月額・年会費は不要で、ATM引き出しにも一定の無料枠が設けられています。
ただしサービス提供地域は主に欧州などに限られ、日本では利用できません。
ポイント連動型(クレジット型): 従来のクレジットカードの後払い機能を利用しつつ、利用額に応じたポイント還元が暗号資産で付与される方式。
日常のカードショッピングで貯まるポイントがビットコインなどに交換されるため、間接的に仮想通貨を得る形です。
例)bitFlyerクレジットカード(アプラス発行・Mastercard)は、月々のカード利用額に対して0.5%〜1.0%相当のビットコインがbitFlyer口座に自動付与されます。
このように「支払いは円建て、還元は仮想通貨」というモデルも登場しています。
以上のようなカードによって、ユーザーは保有する仮想通貨を実店舗やオンライン決済で直接使えるようになります。
海外ではVisaやMastercardが50社以上の暗号資産企業と提携し、こうしたカード発行を進めており、ビットコインで買い物できる環境が整いつつあります。
一方、日本国内でも2020年代に入り金融大手と暗号資産交換業者の協業によるサービス実証が進み、少しずつ類似サービスが登場し始めています。
以下では、具体的なカードの例や国内外の動向について詳述します。
仮想通貨で直接支払いできる主なカードサービス(デビット/プリペイド型)
ビットコイン等での直接支払いを可能にするカードには、主に取引所と連携したデビットカードやプリペイドカードがあります。
それぞれユーザーの暗号資産を即時に法定通貨に変換して決済する仕組みです。
ただし、ほとんど日本ではサービス提供していません。
Crypto.com Visaカード(Crypto.com社): シンガポール拠点のサービスで、プリペイド式のVisaデビットカードです。
Crypto.comアプリから法定通貨または対応する仮想通貨をチャージして利用し、利用時に自動換金されます。
特徴は自社トークンCROのステーキング量に応じたカードランク制度で、上位ランクほどリワードや特典が充実します(最大5%のキャッシュバックや空港ラウンジ利用等)。
ただし日本では現在サービス未提供です。
Binance Visaカード(Binance社): 世界最大級の暗号資産取引所バイナンスが発行するVisaデビットカードです(提供地域は主にヨーロッパ圏)。
ユーザーのバイナンス口座に接続されており、保有する複数の暗号資産残高を決済に充当できます。
利用時に自動で暗号資産を売却して法定通貨へ交換し支払いが行われます。
最大8%をBNBでキャッシュバックするプログラムがありますが、最高還元を得るには600BNB以上(数万ドル相当)の保有が必要で、通常ユーザー向けの還元率は0.1%〜2%程度(保有BNB量に応じ段階制)です。
年会費・発行手数料は無料でATM引き出し手数料も一定額までは無料ですが、地域限定サービスであり日本では利用不可です。
Coinbase Card(Coinbase社): 米大手取引所コインベースのVisaデビットカード。
コインベース口座内の資産で決済でき、利用の度に暗号資産を売却して引き落とします。
利用額の最大4%分の暗号資産リワードが付与される点が特徴で、報酬としてビットコイン(1%程度)やステラルーメン(最大4%)など複数から受け取り通貨を選択可能です。
ただしビットコイン選択時は還元率が低めになるなど通貨によって差があります。
また、USDまたはUSDC残高を使う場合は手数料無料ですが、その他アルトコインを直接使う場合は都度2.49%の売却手数料が課されるため、事前にUSDCへ両替して利用する方が有利に設計されています。
日本では未展開です。
BitPayカード(BitPay社): 米国の老舗暗号資産決済プロバイダBitPayによるMastercardプリペイドカードです。
対応通貨はBTC・BCH・ETH・XRPのほかUSDCやDAI等のステーブルコイン、DOGE・LTCなど多彩です。
BitPayウォレットからカードに暗号資産をロード(チャージ)すると即時に市場レートで米ドルに交換され、ドル建て残高としてカード利用できます。
特徴は暗号資産をドル転する際の為替手数料が不要な点で、ユーザーはネットワーク手数料(マイナー料)のみ負担すればよく、チャージによる隠れコストが少ないことです。
カード発行料・月額費も無料で、ATM引き出しは1回2.50ドルの固定手数料となっています。
現在サービス提供は米国居住者に限られますが、「暗号資産を即座に法定通貨化して使うブリッジ」として機能し、ドル建て決済のため税務処理も比較的明確だと評価されています。
これらのデビット/プリペイド型カードはいずれもVisaまたはMastercardの国際ブランドと提携しており、通常のクレジットカードやデビットカードと同様に世界中の加盟店で使用できます。
ユーザーは暗号資産をチャージするだけで、普段の買い物で仮想通貨を間接的に支払うことが可能になります。
ただし価格変動リスク(利用タイミングでレートが変われば支払額も変動)や税制上の問題(日本では仮想通貨を使うと毎回譲渡所得課税の可能性)といった課題も指摘されています。
特に日本では後述のように税務面の負担が大きく、利用ごとに損益計算が必要になる点には注意が必要です。
カード利用で仮想通貨が還元されるサービス(リワード型)
通常のクレジットカードのポイントやキャッシュバックを暗号資産で受け取れるカードも登場しています。
これはカード決済額に応じて付与されるポイントが自動的にビットコインなどに交換されたり、最初から報酬が暗号資産として付与される仕組みです。
ユーザーは日常の支払いで仮想通貨を貯めることができ、投資感覚でリワードを楽しめます。
bitFlyerクレカ(スタンダード/プラチナ): 国内大手取引所ビットフライヤーがアプラスと提携して発行するMastercardブランドのクレジットカードです。
後払い式ですが利用額に応じてビットコインが還元され、スタンダードカードで0.5%, プラチナカードで1.0%のBTCが毎月bitFlyer口座に付与されます (換算レートは月末時点の価格)。
年会費はスタンダード無料、プラチナは翌年度以降16,500円(税込)かかりますが年間150万円以上の利用で無料になる特典があります。
ビットフライヤーを利用しているユーザーにとって、ポイント管理の手間なく自動で投資用BTCが貯まる点が魅力です。
日本でもサービス提供しているはずです。
https://bitflyer.com/ja-jp/s/lp/creditcard
上記リンクより、申し込みが可能です。
BlockFi Rewards Visa(米国): かつて米BlockFi社が提供していたVisaクレジットカードで、カード利用額の1.5%相当をビットコインでキャッシュバックする仕組みでした。
暗号資産レンディング企業による高還元カードとして注目されましたが、BlockFi社の経営破綻に伴い現在はサービス停止中です。
(※BlockFiカードは2021年に登場し高い人気を博しましたが、2022年の同社破綻により現在新規受付停止)
Gemini Credit Card(米国): 米Gemini取引所が提供するMastercardクレジットカードで、最大3%を仮想通貨で還元します。
具体的には飲食店利用で3%、食料品で2%、それ以外1%が利用と同時にユーザー指定の暗号資産に自動交換され付与される仕組みです。
年会費無料でドル建て決済のため税務計算もシンプルに扱え、暗号資産でのリワード獲得手段として米国ユーザーに利用されています。 日本では未提供です。
Coinbase Card(リワード): 前述のCoinbaseデビットカードも、カード利用時の暗号資産リワード付与という点でリワード型カードとしての側面があります。
米国版では選択する暗号資産によって最大4%(一時期ステラルーメン選択で4〜5%提示)もの高率リワードを得られたこともあります。
クレジットカードではなくデビットカードですが、「普段の支払い=暗号資産獲得」につながる例として代表的です。
日本ではサービス提供していないと思われます。
これら以外にも、米国のFoldカード(Visaデビット、利用額の一部をビットコインで還元するサービス)や、日本では前述のbitFlyerクレカ以外にSBIグループ系カードのポイントを暗号資産に交換する試みなどが見られます。
SBIホールディングスは2025年7月、提携クレジットカードのポイントサービス(アプラス発行カードの「APLUSポイント」)において、貯まったポイントをビットコイン・イーサリアム・XRPに交換できる実証プログラムを開始しました。
これは2100ポイントを2000円相当の暗号資産に交換する小規模な試験運用ですが、日本企業による暗号資産活用推進の一例として注目されています。
このように「ポイント→仮想通貨」という間接的な形も含め、カード利用と暗号資産リワードを組み合わせたサービスが国内外で増えつつあります。
暗号資産取引所が発行するカード一覧
暗号資産交換業者(取引所)自らが発行主体となっているカードも多く存在します。
利用者基盤を活かして自社サービス圏内で経済圏を回す狙いがあり、カード事業単体の収益よりもマーケティングやエコシステム戦略として位置付けられるケースが多いようです。
以下に主な取引所系カードをまとめます。
ほぼすべて日本では利用不可です。
Binance Card(バイナンス) : 取引所口座と連動したVisaデビットカード。
支払い時に自動で口座内の仮想通貨が法定通貨に換算されます。
最大8%をBNBで還元するキャッシュバック制度あり (要大量のBNB保有)。
提供地域は欧州・南米など一部で、日本を含むアジアでは未提供。
Crypto.com Visa(Crypto.com) : Crypto.com取引アプリに紐づくプリペイド(デビット)カード。
自社トークンCROの保有量に応じてランクが分かれ、最大5%のCROリワードや各種特典。
シンガポール発ながら米欧含め展開。
ただし日本未対応。
Coinbase Card(コインベース) : 米コインベースのVisaデビット。
最大4%のクリプトリワード付与。
米国および一部欧州で利用可(日本提供なし)。
利用時にUSDC以外の資産を使うと2.49%の手数料が発生する点に留意。
Bybit Card(バイビット) : 大手取引所Bybitが発行するMastercardデビットカード。
2023年より英国・EEA(欧州経済領域)居住者向けに提供開始し、仮想通貨資金を直接カードで使えるサービスです。
物理カードとバーチャルカードが提供され、カード利用時にはBybit口座の資産を売却して支払いに充当します。
最大10%相当のキャッシュバック(独自ポイント付与)などキャンペーンも展開されていますが、日本居住者は利用不可(2023年時点)です。
将来的に日本上陸の噂もありますが、実現には日本の規制適合が課題となっています。
bitFlyerクレカ(ビットフライヤー) : 日本の取引所が直接関与する例。
詳細は前述の通り、アプラス発行のMastercardクレジットカードで、利用額に応じビットコインが付与されます。
スタンダード/プラチナ2種のカードで還元率が異なり、国内で入手可能な数少ないクリプトカードです。
その他の取引所系カード: 上記の他にも、Geminiクレジットカード(米国)、Krakenカード(欧州でサービス開始予定)、Bitgetカード(一部地域で提供発表)など、各国の主要取引所・ウォレット事業者が相次いで提携カードを発表しています。
中にはNexo(ネクソ)のように暗号資産担保融資の枠を使ったカード(Mastercardデビット) や、Wirexのように複数法定通貨と暗号通貨に対応したVisaカード など特色あるサービスも見られます。
これらは交換業者の顧客囲い込み策であると同時に、暗号資産ユーザーへの利便性提供という側面があります。
日本国内で入手・利用可能なカードと申込条件
日本国内で利用できる仮想通貨関連カードは2025年現在まだ限られていますが、少しずつ増えてきています。
主なカードとその概要は以下の通りです。
bitFlyer VISAプリペイドカード(ビットフライヤー): 日本初(2020年提供開始)の仮想通貨対応プリペイドカードです。
ビットフライヤーの口座からビットコインを日本円にチャージし、全国のVisa加盟店で利用できます。
年会費・発行手数料は無料、本人確認済みのbitFlyerユーザーであれば申し込み可能です。
発行主体はプリペイドカード事業者の株式会社カンム(VANDLEカード)であり、利用上限はチャージ1回3万円・月12万円までなど一定の制限があります。
事前チャージ式のため審査不要で18歳以上なら誰でも発行可能とされています(ただし未成年の場合親権者の同意等が必要な場合あり)。
仮想通貨をすぐ円に換えて使える手軽さから、国内ユーザーに利用されています。
bitFlyerクレジットカード(ビットフライヤー/アプラス): 前述の通り日本国内で数少ないクリプトリワード型クレジットカードです。
申し込みにはビットフライヤーの口座開設および所定の審査が必要で、発行会社のアプラスによる与信審査があります。
個人向け専用(法人申込不可)で、18歳以上(高校生除く)の日本在住者が対象です。
国際ブランドはMastercardのみで発行されます。
初年度年会費無料(スタンダードは以降も無料、プラチナは2年目以降税込16,500円)ですが、年間利用額150万円以上で翌年度無料になる優遇があります。
カードショッピング利用金額に対しスタンダード0.5%、プラチナ1.0%のビットコインが翌月付与される仕組みで、普段のカード利用で自動的にビットコイン資産を形成できる点がメリットです。
Slash Card(Slash Fintech株式会社): 2025年提供開始予定の日本初の暗号資産担保型クレジットカードとして注目されています。
米ドル連動ステーブルコインUSDCをユーザーが担保(デポジット)として預け入れることで、その範囲内で後払い決済(BNPL型の与信)を利用できる仕組みです。
いわば「手元のUSDC=クレジット枠」として、実店舗では通常の国際ブランドカード(Visa/Mastercard)として決済でき、後日利用額分のUSDCを精算する形になります。
日本の資金決済法等の規制に準拠した初のクリプトクレジットカードであり、セルフカストディ型ウォレットと連携してユーザー自身が資産を管理しつつカード決済できる点が特徴です。
利用条件は18歳以上の日本在住者でKYC(本人確認)必須とされ、β版では招待制で提供が開始されました。
年会費無料で物理カードとバーチャルカードを選択可能、海外利用もできます。
仮想通貨の価値を担保に後払いで使えるため、「暗号資産を売却せずに日常決済に充当できる」画期的な仕組みとして期待されています。
もっとも利用ごとに生じる含み益の課税計算はユーザー側で対応する必要がある点が明記されています。
現状、国内で公式に提供されている暗号資産対応カードは上記程度で、他の取引所(コインチェック、GMOコイン、DMMビットコイン等)は類似サービスを提供していません。
海外のBinanceやCrypto.comカードは日本居住者向けには未提供であり、日本国内で利用可能な範囲は限定的です。
しかし、ビットフライヤーやSlashの例のように金融庁登録済み業者と提携した形でサービス開発が進みつつあり、今後選択肢が徐々に増える可能性があります。
日本における法規制と発行可否の現状
日本では2017年の法改正でビットコインなど暗号資産が決済手段として法律上認められました(改正資金決済法により「暗号資産」として定義)。
その結果、暗号資産交換業者の登録制・監督強化などユーザー保護のための規制整備が進み、暗号資産を用いたサービス提供には厳格なルール遵守が求められています。
クレジットカード会社による自主規制もその一つで、2018年前後より日本の主要カード各社は自社カードでの暗号資産購入取引を禁止する措置を取りました。
これに伴い、国内取引所(例えばコインチェック等)でもクレジットカード決済による仮想通貨購入サービスが停止されています。
要するに、「日本国内ではクレジットカードで直接仮想通貨を買うことは原則できない」状況となっています。
この制限はカード利用者側に対するものというより、「過剰な借入で仮想通貨投機を行うリスク」や「不正利用・債務未回収リスク」を抑えるためにカード会社が設けたルールです。
したがって、クレジットカードそのものに仮想通貨機能を付帯するサービス(ポイント還元を仮想通貨にするといった間接的な形)は直ちに禁止対象ではありません。
また、プリペイド型やデビット型であれば利用毎に即座に法定通貨に変換されるため、「カード会社としては通常の円建て決済と同じ」であり提供可能な余地があります。
実際、bitFlyerプリペイドやクレカのように交換業者が関与しつつも法定通貨建てで決済処理されるサービスが提供されています。
この場合、仮想通貨の売買部分は登録業者(交換業者)が担い、カード決済部分はカード会社が担うことで法制度の枠内に収めています。
もっとも、日本で暗号資産を日常決済に使う上で最大のハードルは税制面の課題です。
日本では暗号資産を売却した際に生じる利益(値上がり益)は雑所得(または譲渡所得)として課税対象となります。
日常の買い物で少額を使っただけでも、その仮想通貨を取得した時点との差額利益が出ていれば課税される可能性があります。
つまり「コーヒー1杯買うたびに確定申告が必要」という状況になりかねず、ユーザーにとって非常に煩雑です。
このため日本のユーザーが仮想通貨払いに踏み切るハードルは高く、カード事業者側も普及に慎重でした。
Slash CardのようにUSDC担保・ドル建て与信とすることで税務上の扱いを簡素化しようという動きもありますが、それでも担保するUSDC自体をどう入手したか(他の変動する仮想通貨を売ってUSDCに換えた場合はその時点で課税)など課題は残ります。
規制当局はマネロン対策やユーザー保護の観点から暗号資産絡みの新サービスに慎重ですが、一方でキャッシュレス促進やWeb3推進の文脈では健全なクリプト決済サービスなら容認する姿勢も見られます。
実際、金融庁も登録済み業者による実証実験には理解を示しており、2023年以降はステーブルコイン解禁(改正資金決済法の施行)など環境整備も進みました。
Slash Cardは「日本の法規制に準拠した初のサービス」として関係各所と協議の上で発行に漕ぎ着けており、今後も法の範囲内であれば暗号資産連携カードの発行は可能と言えます。
重要なのは、カード利用時の換金プロセスを適切に管理できる交換業者や決済事業者との提携です。
ビットフライヤーやSBIグループなど信頼性の高い企業が発行母体にいるカードは比較的スムーズにサービスインしており、逆に未登録の海外業者などが日本向けにカード発行することは困難です。
総じて、「日本では暗号資産カードの発行自体が法で禁止されているわけではない」が「税制や自主規制など間接的なハードルが高い」ため、慎重に枠組みを整えた上で一部サービスが提供され始めている段階と言えるでしょう。
国内外の主な仮想通貨関連カードサービス比較
以下に、海外および日本国内の代表的な仮想通貨対応カードの特徴を比較表でまとめます。
主な海外の暗号資産対応カードサービス
- サービス名(発行主体)— カード種別— 国際ブランド— 還元・報酬内容— 提供地域・対象
- Crypto.com Visaカード(Crypto.com) — プリペイド式デビット(前払い)— Visa— 最大5%をCROでキャッシュバック ※自社トークンのステーキング条件あり— 米国・欧州・アジア等※日本未対応
- Binance Visaカード(Binance取引所) — デビット(即時決済)— Visa— 最大8%をBNBで還元 ※保有BNB量に応じ0.1〜8%段階制 — 欧州(一部国)・南米等※日本未対応
- Coinbase Card(Coinbase取引所) — デビット(即時決済)— Visa— 最大4%を暗号資産でリワード付与 ※報酬通貨はBTC・XLMなど選択可— 米国・英国・EU圏※日本未対応
- BitPayプリペイド(BitPay社) — プリペイド(チャージ式)— Mastercard— 還元なし(チャージ時に即ドル転)※為替手数料無料で即時法定通貨化 — 米国(居住者限定)
日本国内の主な暗号資産対応カードサービス
- サービス名(発行主体)— カード種別— 国際ブランド— 還元・支払い方法— 日本での利用可否
- bitFlyer VISAプリペイド(bitFlyer+VANDLE) — プリペイド(チャージ式)— Visa— 事前にBTCを円換算チャージして支払い ※還元なし— ○ (日本居住者向け)
- bitFlyerクレジットカード(bitFlyer+アプラス) — クレジット(後払い)— Mastercard— 利用額の0.5〜1.0%をBTC付与 ※スタンダード0.5%、プラチナ1.0%— ○ (日本国内で発行)
- Slash Card(Slash Fintech) — クレジット(後払い)— Visa/Master [※]— USDC担保の与信枠内で決済 ※後日USDCで精算(BNPL型)、還元未発表— ○ (β版提供中)
[※] Slash Cardは国際ブランド各社と協議中で、正式提供時にVisaまたはMastercardブランドで発行予定。
表の解説: 上表のとおり、海外主要サービスではCrypto.comやBinanceのように高率キャッシュバックを謳うカードが多いものの、いずれも日本では利用できません。
一方、日本国内サービスではbitFlyerやSlashといった例がありますが、還元率や利用枠は海外に比べると控えめです。
しかし国内版は円建て決済ゆえに法規制や税制への配慮がなされている点が特徴です。
例えばbitFlyerクレカは通常のポイント還元と同様に扱われ、Slash Cardは担保型で与信枠を設けることで日本の法律に適合させています。
どちらも金融庁登録業者の仕組みを通して提供されており、安全性・法令順守を重視した設計になっています。
おわりに(最新動向と展望)
仮想通貨対応カードは、暗号資産を「投資資産から日常の決済通貨へ」と昇華させる試みとして世界的に注目されています。
現在は各種課題(価格変動リスク、税務処理、ユーザー認知など)があるものの、カード大手や金融機関もWeb3時代を見据えた取り組みを加速しています。
VisaやMastercard自体が暗号資産企業と提携を深めており、将来的には仮想通貨決済が一般の電子マネーやクレジット決済と並ぶ存在になる可能性も指摘されています。
日本においても、2023年の規制緩和(ステーブルコイン解禁など)や大手企業の参入で状況は変化しつつあります。
Slash Cardの登場はその一里塚であり、今後税制面の整備やユーザビリティ向上が進めば「暗号資産で日常支払いをする時代」が訪れるかもしれません。
現時点では利用できるカードが限られるため、本調査を参考に自分の用途に合ったサービスを見極めつつ、最新情報を追っていくことが重要です。
一歩ずつではありますが、仮想通貨とクレジットカードの融合は着実に前進しており、新たなキャッシュレスの形態として今後も発展が期待されます。
参考文献・情報源: 本稿では各カード公式サイトや暗号資産専門メディアの記事、法律解説資料 等の最新情報に基づき取りまとめを行いました。
各種データや制度については引用箇所に示した出典をご参照ください。

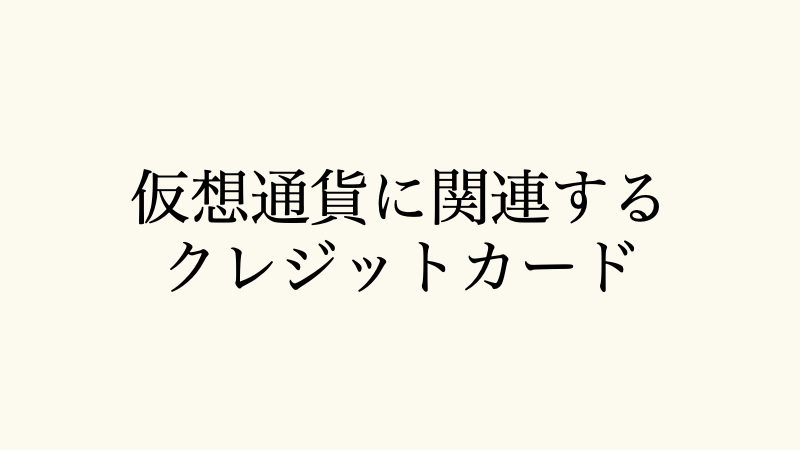
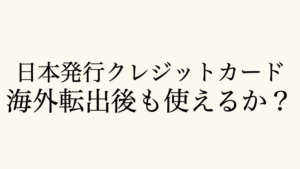
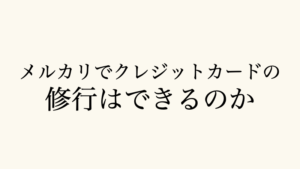
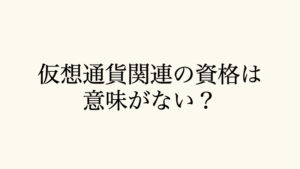

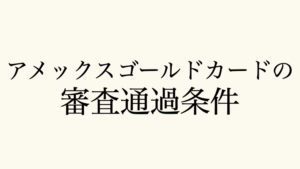

コメント