あくまで、巷で言われている傾向ですので、これに従えば絶対に勝てるというものではありませんので、注意してください。
過去の7月におけるドル円の季節傾向
ドル円(USD/JPY)は例年7月に独特の季節性パターンを示すことが知られています。
過去5〜10年を振り返ると、7月はドル安・円高に振れやすく、月足ベースで下落するケースが比較的多い傾向があります。
たとえば直近10年間では7回も7月にドル円が下落しており、その平均下落率は約-1.3%にも達しました。
過去20年という長期統計で見ても、7月は主要なクロス円通貨ペアの多くで陰線(月初より月末が円高)となる割合が陽線を上回っており、全体的に円高(円の独歩高)になりやすい月と言えます。
このアノマリーは最近数年で顕著であり、歴史的な円安トレンドとなった2022年ですら7月にドル円が約10円急落する局面が見られました。
つまり、強いドル高局面であっても7月になると調整的な円高が繰り返される傾向があるのです。
典型的な価格パターンとボラティリティ傾向
7月のドル円相場には月内での特徴的な値動きパターンも指摘されています。
日本には「七夕天井・天神底」という経験則があり、7月初旬(七夕前後)に高値を付けた後、月末(7月24〜25日頃)にかけて底打ち(円高のピーク)するというものです。
実際、過去20年のデータでも7月3日や7月9日といった月前半に円安(ドル高)となりやすい日が多い一方、7月24日は米ドル/円が下落(日足陰線)となる確率が86%にも達しており、月末に向けてドル安・円高に転じる傾向が確認できます。
このように、7月前半はリスク選好の円安が進みやすくても、中旬以降に反転して円高基調となりやすい点に注意が必要です。
また、ボラティリティ(変動率)の面でも7月には一定の傾向があります。
夏場は市場参加者が減少することもあり一見穏やかに見えますが、過去の統計によればドル円の7月の平均高安レンジは約4円73銭(473.81 pips)にも達しています。
これは平年ベースで5円前後の値幅が動く計算になり、6月に比べて停滞しがちな年でも、7月には再びボラティリティが上昇する可能性を示唆しています。
事実、夏場の円高アノマリーが顕在化する年には急激な変動も起こり得て、例えば2010年の7月中旬〜8月初旬に約-7.9%もの急落、2024年にも同時期に約-7.2%の急落が記録されています。
市場では7月に債券利回りが低下しボラティリティが高まる局面では円高が進みやすいことも知られており、油断できない月と言えるでしょう。
重要経済指標と中央銀行イベントの影響
7月は経済指標の発表や金融政策イベントが集中しやすい月でもあります。
米国では月初に前月分の雇用統計(非農業部門雇用者数/NFP)が発表され、その後も月中旬に消費者物価指数(CPI)などインフレ指標、そして月末近くに連邦公開市場委員会(FOMC)が控えています。
日本でも7月下旬に日銀金融政策決定会合が開催されるのが通例であり、とくに近年はFOMCと日銀会合がほぼ同時期(場合によっては同じ週や同日)に行われるため、市場へのインパクトは一層大きくなります。
こうした重要イベント時には、一方向に傾いていた相場の巻き戻しが起こりやすい点も覚えておきましょう。
たとえば2022年7月には、米FOMCに先立つ米6月CPIが市場予想を下回ったことを契機にドル買い・円売りのポジション解消が進み、ドル円が145円から138円台へ急落しました。
また2019年7月には米連邦準備制度が約10年ぶりの利下げに踏み切り、市場の利下げ観測前倒しでドル円が下落基調となるなど、FOMCの結果次第で短期的なトレンド転換が発生しています。
日銀サイドでも7月会合で金融緩和策の調整やサプライズ政策変更(例えばYCC柔軟化やテーパリング示唆)が行われれば、薄商いの中で円買いが一気に進む可能性があります。
さらに、日本独自の要因として7月初旬には日銀短観など企業景況感指数の発表、月末には全国消費者物価指数(CPI)や雇用統計なども控えていますが、これらは米金融政策動向と相まってドル円に影響を及ぼすことになります。
総じて7月は重要イベントが目白押しであり、その結果次第でドル円の短期的なトレンドが大きく変化しやすい点に留意が必要です。
夏枯れ相場による流動性の変化
「夏枯れ相場」と呼ばれるように、夏季(7月中旬から8月)には市場参加者の減少による流動性低下が起こりやすくなります。
特に欧米では7月初旬の米独立記念日から8月〜9月初頭の休暇シーズンにかけてマーケットが夏休みモードに入り、出来高が細る傾向があります。
流動性が低い状況下では、一見値動きが緩慢になりレンジ相場になりやすい面がありますが、その反面少ない注文で相場が動きやすくなるため、予想外のニュースやイベントが出た際に価格変動が増幅されるリスクも高まります。
実際、夏場は平時は小動きでも、突発的な地政学リスクや要人発言などが引金となって瞬間的な急変動(いわゆるフラッシュクラッシュ的な動き)が起こるケースも過去に見られました。
特に7月末〜8月は主要参加者が不在になりがちなため、重要イベント時の値動きには普段以上に注意が必要です。
なお夏季は世界的には株式市場が上昇しやすい「サマーラリー」の局面でもありますが、リスクオン相場が進む際には日本から海外への資金流出(円売り)が増える一方で、日本企業や機関投資家による中間期のリパトリ(海外投資資金の本国回帰)も起こりやすく、これが円買い要因となる場合もあります。
例えば国内金利の上昇局面では、海外債券運用から国内債への資金シフトが進みやすく、夏場に円買い圧力となる可能性があると指摘されています。
総合すると、夏枯れ相場下のドル円は取引薄による一時的なレンジ形成と想定外の急変動の両方に備える必要があり、市場心理の変化やフローの動向を普段以上に注視することが求められます。
7月相場で狙える短期〜中期戦略の例
最後に、上述の傾向を踏まえた7月におけるトレード戦略の一例をいくつか紹介します。
季節性やイベントドリブンの動きを利用することで、夏場のドル円相場から収益機会を見出すことも可能です。
「七夕天井・円高アノマリー」を利用した逆張り戦略: 7月初旬にドル円が上昇(円安)した局面では強気の追随は控え、むしろ月前半の高値圏でドル円の売りポジションを構築し、中〜下旬の反落(円高)局面を狙う戦略です。
過去の統計が示すように7月24日前後には高確率で円高転換する傾向があるため、利益確定目標を月末前後に設定すると季節要因を味方につけられます。

実際に、この期間(6月中旬〜9月初め)にドル円ショートを持ち続ける戦略は過去25年で72%の勝率を残し、年率換算-6%超の平均的な下落を捉えてきたとの分析もあります。
イベントドリブン戦略(ブレイクアウト狙い): 7月末のFOMCや日銀会合などのビッグイベント直前にはポジションを軽くし、結果発表時のボラティリティ拡大を利用する戦略です。
具体的には、重要イベント前に狭まったレンジ相場でオプションのストラドル/ストラングル戦略や逆指値注文を準備し、発表直後の急変動でブレイクアウトを狙う方法が考えられます。
特にサプライズ(金利サプライズや政策変更)が予想される場合には、その方向へ事前に小さく仕掛けておき、思惑通りに動けば追随、外れた場合でも損切りを徹底する姿勢が重要です。
過去にもFOMCや日銀会合が同時期に行われた際には相場が大きく跳ねるケースがあったため、指標発表カレンダーを睨んだ柔軟なトレードが有効でしょう。
キャリートレードのヘッジ戦略: 高金利通貨を買ってスワップ収益を狙うポジションを保有している場合、7月〜8月はその逆風となりやすい季節です。
実際、トルコリラ/円やメキシコペソ/円、南アフリカランド/円などは過去20年で7〜8月に陰線(月足ベースの円高)となる頻度が高く、7月は20回中14回も円高で終わっています。
このため、ドル円も含め円売りのキャリートレードを仕掛けている場合は、夏場に一時ポジションを縮小したりオプションで下値ヘッジを行うなど、防御を固める戦略が推奨されます。
円高局面が一時的と判断できる場合は、その調整局面で新規に安値拾い(押し目買い)を狙う準備も有効ですが、深押しリスクに備えた資金管理が不可欠です。
レンジ&ブレイク併用戦略: 夏枯れで市場参加者が減少している間、明確なトレンドが出にくければ狭いレンジ内での逆張り売買(サポート近辺で買い・レジスタンス近辺で売り)も短期的には有効です。
実際に2023年7月前半のように、材料難から143~145円程度のレンジでもみ合う場面では、小刻みな値幅取りが可能でした。
しかし薄商いの中で突発ニュースが出ると一気にレンジブレイクする恐れもあるため、利小損小の徹底やブレイク時の順方向への追随も視野に入れておきます。
平均的な7月の値幅は約5円程度と想定されることから、平時はその範囲内での収益機会を狙いつつ、想定レンジを超える動きが出た場合にはトレンドフォローに切り替える柔軟性が求められます。
以上、ドル円を中心とした7月相場の過去傾向と留意点、および戦略例を概観しました。
過去のパターンはあくまで確率的な傾向であり、必ずしも今年も同じ動きになるとは限りません。
しかし、季節性やイベントスケジュールを把握しておくことはリスク管理とチャンス発見に有用です。
夏相場ならではの流れを踏まえつつ、最新の経済指標や市場心理の変化にもアンテナを張り、柔軟なトレード計画を立てることが重要と言えるでしょう。

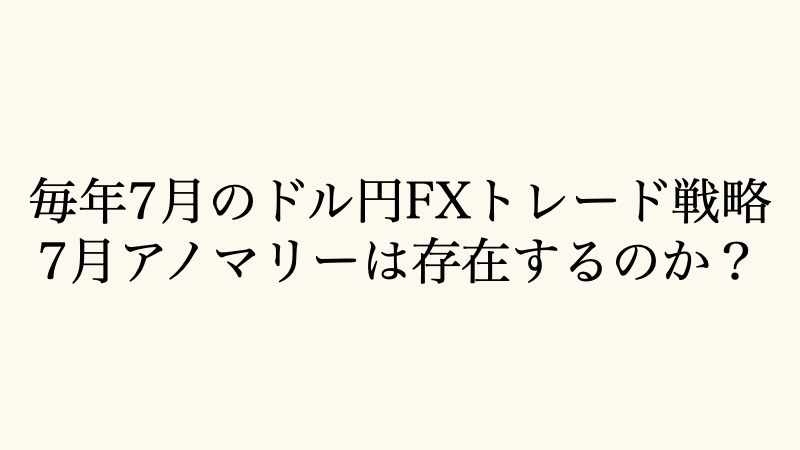

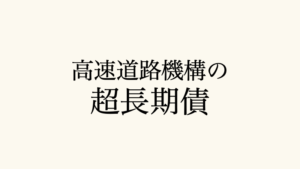
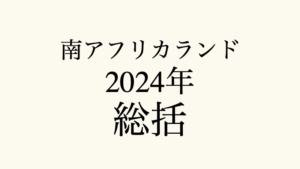
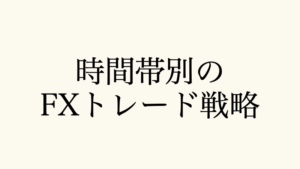
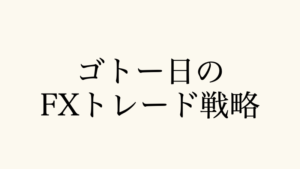
コメント