日本全体の傾向と地域差
日本のITエンジニアの年収には地域差があり、首都圏と地方で顕著です。
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によれば、ITエンジニアの平均年収は東京都で約580万円、大阪府で約520万円、地方都市では約450万円と最大130万円もの差があります。
この差は単なる物価水準の違いだけでなく、首都圏にIT企業が集中し大型案件が多いことなどが影響しています。
実際、地方勤務のエンジニアからは「地方だと年収350~400万円程度の求人が多い」という声もあり、都市部と地方では求人水準に開きがあるのが現状です。
また、東京など都市部ではIT人材不足から多少高給でも人材を確保しようとする動きがある一方、地方では競争が緩やかで給与水準が抑えられる傾向があります。
このように都市部と地方では平均年収に大きな開きがあり、基本情報技術者試験(以下、基本情報)を取得していても勤務地域によって年収に差が出ることが考えられます。
所属業界・職種による年収差(SIer・SES・Web系・自社開発・社内SE)
ITエンジニアの年収は、所属する業界や職種によっても大きく異なります。
システムインテグレータ(SIer)では、大規模案件を扱う元請け企業ほど年収が高い傾向があります。
例えば、大手SIer企業の平均年収は野村総合研究所で1,235万円、電通国際情報サービスで1,057万円など非常に高水準です。
一方で下請け層のSIerでは受注単価が低く、エンジニアの年収も抑えられがちです。
実際、日本のIT業界はゼネコン型の多重下請け構造になっており、下流工程を担う企業ほど安い単価で大量の業務を引き受けるため、下層のエンジニアは労働量の割に報酬が低くなる仕組みです。
その結果、SIer業界でも一次請け(元請け)か下請けかで年収に大きな差が生じ、「給料が高いのは元請けだけ」という指摘もあります。
SES(システムエンジニアリングサービス)業界では、エンジニアの平均年収は約460万円程度とされています。
SESは契約形態上、エンジニア個人の作業に対して料金が発生するビジネスモデルで、中間マージンが差し引かれるため給与水準が上がりにくい側面があります。
ある調査では「SESだと10年働いても年収500万円を超えるのは難しい」という声もあり、多重下請け構造による中間マージンが年収上昇の壁になっていると指摘されています。
基本情報を取得していても、SES企業のように構造的に単価が低い職場では大幅な年収増が見込みにくい状況です。
Web系・自社開発系企業では、企業やスキル次第で年収幅が大きくなります。
自社サービスを持つWeb系企業は成長企業も多く、スキルの高い人材には高年収を提示する傾向があります。
例えば、上場している主要Web系企業では平均年収がサイバーエージェント772万円、ヤフー651万円などと報告されています。
一方、大手SIerと比較するとWeb系企業全体の平均では必ずしも極端に高いわけではなく、「Web系よりSIerの方が給料が高い場合もあるが、それはB2Bで客単価が高い元請けに限られる」との指摘があります。
実際にはWeb系でもスタートアップなどでは給与水準が抑えめなケースもあり、業界内での企業規模や収益構造の違いが年収に反映されます。
社内SE(社内情報システム担当)の場合、一般に言われるのは「安定しているが突出して高給ではない」という傾向です。
社内SEの平均年収は調査によって幅がありますが、求人データでは450万~580万円前後との報告があります。
例えばDODAの職種別データでは社内SEの平均年収は450.8万円と、ITエンジニア全体の平均と比べてやや低めでした。
社内SEは企業内のコストセンターとして位置付けられることが多く、利益に直接貢献しにくい点から給与テーブルも保守的になりがちです。
ただし、大企業の情シス部門や高度なスキルを持つ社内SEでは600万円以上の事例もあり、企業規模や担当するシステムの重要度で差が出ます。
以上のように、基本情報技術者試験に合格していても、所属する業界や企業次第で年収には大きな開きがあります。
特に多重下請け構造のSIer/SES業界では資格より経験・立場がものを言いやすく、資格取得者でも年収が伸び悩むケースが多いと考えられます。
基本情報技術者資格の市場価値と企業での評価
基本情報技術者試験(FE)は国家資格ではありますが、その市場価値は「ITエンジニアとして最低限身につけておくべきレベル」と位置付けられることが多いです。
取得していることで「基礎的なITスキルを有する証明」にはなりますが、それ自体で高度なスキルを担保するものではありません。
実際、基本情報を持っている人は業界内に多数おり、合格者の平均年齢も25歳程度と若年層が中心であることから、企業側の評価も「新人・若手の登竜門をくぐった」程度の認識に留まる場合があります。
企業の中には基本情報の取得を社員に推奨し、受験料補助や合格報奨金を出すところもあります。
これはIT基礎力の証明として一定の評価をしている証拠ですが、一方で資格手当の金額設定を見ると市場評価の度合いがわかります。
一般的に基本情報資格に対する毎月の資格手当は5,000円~10,000円程度、合格時の一時金も2~10万円程度が相場です。
例えば応用情報技術者(基本情報の上位資格)では手当相場が5,000~20,000円、一時金5~20万円で、基本情報の約2倍の水準になっており、企業から見た重要度の違いが現れています。
基本情報そのものの手当額は決して高額ではなく、「ベーシックな資格のため大きな手当は期待できない」とも言われています。
これは基本情報が独占業務を付与するような資格ではなく、取得しても即収入につながりにくいことを示しています。
また、外資系企業においては基本情報の認知度・評価は低い点も市場価値を下げる要因です。
基本情報は日本独自の国家資格であるため、外資系やグローバル企業では重視されず、代わりにAWS認定やOracle、Ciscoのベンダー資格など国際的に通用する資格の方が評価されがちです。
総じて、基本情報技術者の資格単体の市場価値は「持っていればプラスだが、飛び抜けたアピールにはならない」という位置づけです。
企業側も「新人なら持っていて当然」というスタンスのことが多く、より高度な資格や実務経験と組み合わせて初めて大きな評価につながる傾向があります。
他の資格との比較(応用情報、AWS認定、Oracle Masterなど)
基本情報技術者試験と他資格を比較すると、その価値や年収への影響の違いが見えてきます。
まず応用情報技術者試験(AP)は基本情報の上位に当たる国家資格で、企業からの評価も基本情報より高めです。
前述の通り、資格手当・報奨金の相場でも応用情報は基本情報の2倍程度となっており、社内評価や転職時のアピール度合いでも「基本情報より応用情報を持っている方が知識が深い」と判断されるケースが多いです。
また、基本情報を飛ばして応用情報から取得するエンジニアもいるほどで、スキルアップ志向の人には応用情報の方がステップアップに直結すると考えられています。
クラウドやデータベース系のベンダー資格との比較では、たとえばAWS認定資格(AWS認定ソリューションアーキテクトなど)やOracle Masterなどは特定分野の実践スキルを証明する資格です。
外資系や先端技術を扱う企業では、基本情報よりこれらベンダー資格の方が評価が高い傾向があります。
理由として、AWSやOracleの資格は即戦力のスキル証明となりやすく、市場ニーズに直結しているためです。
例えばAWS認定資格保有者はクラウド人材不足の追い風もあり、転職市場でも高く評価される傾向があります。
一方、基本情報は広く浅い知識の証明であり専門性が示せないため、たとえば「クラウド構築ができる人が欲しい」という求人ではAWS資格の方が重視され、「データベースの専門家が欲しい」という場面ではOracle MasterやDBスペシャリスト資格の方が有利です。
ただし、他の資格と比較した基本情報の強みもあります。
それは裾野の広さと国家資格としての信頼性です。
ITパスポートより難しく応用情報より基礎的な位置付けの基本情報は、「日本国内では無敵な国家資格」とも評され、特に国内の中小企業やSIerでは一定の信頼ブランドになっています。
一部の大企業や公的機関では基本情報の合格を昇進要件や新卒採用時の評価ポイントにしている例もあり、幅広いIT人材の共通ベースラインとして機能しています。
他資格が専門特化であるのに対し、基本情報は汎用的なITリテラシー証明のため、未経験者の登竜門としての価値は依然高いと言えます。
まとめると、応用情報や高度区分資格は基本情報より高評価・高年収に直結しやすく、AWSやOracle等のベンダー資格は需要に直結して評価されやすいです。
一方で基本情報は「無いよりあった方が良いが、それだけでは決定打になりにくい」資格であり、他の資格取得や経験を積むステップとして位置付けられるケースが多いです。
未経験者求人における資格保有者の扱い
基本情報技術者試験の合格者は、未経験者向けの求人市場で一定のプラス評価を受けます。
IT未経験であっても基本情報に合格していれば「ITの基礎知識を自主的に習得した人物」として前向きに捉えられるため、書類選考などで有利になることがあります。
実際、IPA(情報処理推進機構)の資料でも「基本情報はITエンジニアを目指す方の登竜門」と位置付けられており、新卒学生や他業種からの転職者がスキル証明として活用しています。
未経験者歓迎の求人において企業が基本情報取得者に期待するのは、最低限のITリテラシーと学習意欲です。
ある調査によれば、求人情報で「基本情報技術者資格」をスキル要件に検索したところ198件ヒットし、そのうち24件は未経験者歓迎の求人だったといいます。
未経験者歓迎求人の年収条件を見ても、加重平均で約617万円と、経験者向け求人の平均よりやや低い水準でした。
この差は即戦力ではない分控えめな提示になっているためですが、それでも未経験可求人で600万円前後が提示される背景には、基本情報取得者であれば一定の戦力化が見込めると企業が判断している面があります。
言い換えれば、基本情報を持っている未経験者は「ポテンシャル採用」の有力候補になりやすいということです。
もっとも、未経験からIT業界に入った場合、当初の年収は資格の有無にかかわらず300万円台後半~400万円程度に設定される求人が多いのも現実です。
資格手当が出る企業でも月数千円〜1万円程度が加算されるに過ぎず、大幅な差とはなりません。
そのため基本情報を持っているからといって未経験の初任給が飛躍的に高いわけではなく、待遇面では「多少の上乗せ」や「書類通過率向上」に寄与する程度です。
企業としても「未経験だが資格あり」の人材は育成前提と捉えるため、まずは資格よりも現場での適応力や吸収力が重視されます。
したがって、基本情報取得者である未経験者は採用上は有利でも、入社後は他の新人と同様に経験を積んで実力で年収を上げていく必要がある点に留意が必要です。
年収が上がりにくいキャリアパス・職場環境の要因
基本情報技術者試験を取得してキャリアをスタートしても、その後のキャリアパスや職場環境によっては年収がなかなか上がらないことがあります。
主な要因として以下が挙げられます。
多重下請け・下流工程に固定されるキャリアパス: 前述の通り、下請け構造の企業では頑張っても単価の低い仕事が多く、昇給幅に限界があります。
若手のうちは重要な仕事を任されにくく、下流の雑務的な開発や保守に追われてしまい、「作業時間が多い割に給料が安い」という悪循環に陥りがちです。
基本情報を持っていても、キャリア初期に下流工程ばかり経験しているとスキルが偏り、転職市場でも高い評価を得にくくなります。
その結果、年収レンジの低いまま停滞する恐れがあります。
年功序列型の評価制度: 日本企業の多くは未だ年功序列の色彩が強く、IT業界も例外ではありません。
このため、若いうちはいくらスキルアップしても給与に反映されにくい傾向があります。
実際、「高いスキルより年齢や勤続年数の方が評価されるため、スキルを磨いても給料が上がらない」との指摘があります。
基本情報取得者は若手が多いこともあり、年功序列の仕組みの中では資格を取ってすぐ大幅昇給とはなりにくいのが現状です。
重要なポジションも若手には与えられにくく、結果として昇進・昇給の機会が遅れがちになります。
長時間労働と自己研鑽時間の不足: SIerやSESなどで忙しく働く場合、慢性的な長時間労働により新たなスキル習得のための勉強時間を確保できない問題があります。
技術革新の早いIT業界において、勉強や自己研鑽ができないと市場価値が頭打ちになり、結果として年収アップに繋がるようなスキルが身につかない悪循環に陥ります。
基本情報取得までに身につけた知識も、実務で更新されなければ数年で陳腐化しかねません。
職場環境が新技術に挑戦させてくれない、あるいは慢性的な残業で自主学習ができない、といった状況は年収停滞の一因です。
評価制度・人事制度のミスマッチ: 企業によってはITエンジニアのスキル評価が適切でない場合もあります。
例えば「資格を取っても社内で評価されない」「成果よりも上長へのアピールが昇給に影響する」等の環境では、いくら基本情報や他の資格を取っても報われません。
所属企業の評価制度が旧態依然としていると、資格取得者でも年収が上がりにくいと言えます。
特にITに理解の薄い非IT企業の情シス部門などでは、この傾向が強いことがあります。
以上のような要因から、基本情報取得後のキャリアで年収を上げていくには、なるべく上流工程に進む、最新技術に携われる環境に身を置く、評価制度の整った企業へ転職するといった戦略が必要になります。
逆に言えば、SIer下請けでコーディングだけを続ける、長時間労働の職場でスキル停滞する、年功序列企業で待ちの姿勢になる——このようなキャリアパスだと資格を持っていても年収は伸び悩み、「基本情報を取ったのに年収が上がらない」と感じる原因になるのです。
転職市場での評価と年収相場
転職市場において基本情報技術者試験合格者は一定の評価を得られますが、それだけで高年収が保証されるわけではありません。
人材紹介会社の公開求人データによると、基本情報資格を保有スキルに含めて求人検索した場合、ヒットした求人の年収レンジは下は年収300万円台から上は1000万円超まで非常に幅広く分布しました。
この調査では求人全体の加重平均年収が674万円程度となっていますが、高年収帯の求人はリーダー職や高度なスキルを伴うポジションが多く、そうした求人では基本情報に加えて実務経験や他の専門知識が求められるのが通常です。
つまり、転職市場で基本情報保持者が提示される年収相場は、経験次第で大きく異なるということです。
実際の年収相場感としては、基本情報レベルの知識を持つエンジニア(プログラマ・SE)の平均は前述のように400万~600万円台がボリュームゾーンです。
基本情報取得直後の20代前半では年収350~450万円程度が一般的で、30代で500~600万円、40代で管理職になれば700万円以上もあり得るというカーブになります。
重要なのは、基本情報の資格それ自体よりも「その人の経験・スキルセット」によって市場価値が決まる点です。
たとえば同じ基本情報保持者でも、レガシーシステム保守だけをしてきた人と、最新のクラウド開発をリードしてきた人とでは、転職時に提示される年収は大きく異なります。
基本情報は持っていて当たり前という企業も多いため、転職活動では「資格+〇〇の経験」という組み合わせで評価される傾向があります。
なお、基本情報を応募要件に掲げる求人が多いことも一つの特徴です。
によれば、「基本情報を必須もしくは歓迎資格とする企業求人が非常に多い」とされており、特にエンジニア職の採用では基本情報を合否判断の材料にする企業もあります。
その意味で、転職市場では基本情報は持っていないと土俵に立てない場合がある資格とも言えます。
しかし裏を返せば、資格を持っている人同士での競争になるため、結局ものを言うのは実務実績になります。
企業側も「基本情報+何らかの開発経験」「基本情報+応用情報」など総合的に候補者を評価します。
総合すると、基本情報技術者試験の取得者に対する転職市場での年収相場は、経験ゼロでは400万円前後、数年の開発経験を積めば500~600万円前後、10年以上のキャリアでマネジメント経験もあれば700万円以上も可能というイメージになります。
資格単体で見れば平均年収515万円程度とのデータもありますが、これはあくまでその資格を持つ層の一つの目安に過ぎません。
重要なのは資格取得後にどうキャリアを積み上げ、市場価値の高いスキルを身につけるかであり、それ次第で年収は大きく変動します。
したがって、「基本情報を取ったのに年収が低い」と感じる場合、地域や業界の年収相場、自身の経験値、企業の評価制度など様々な要因を点検する必要があるでしょう。

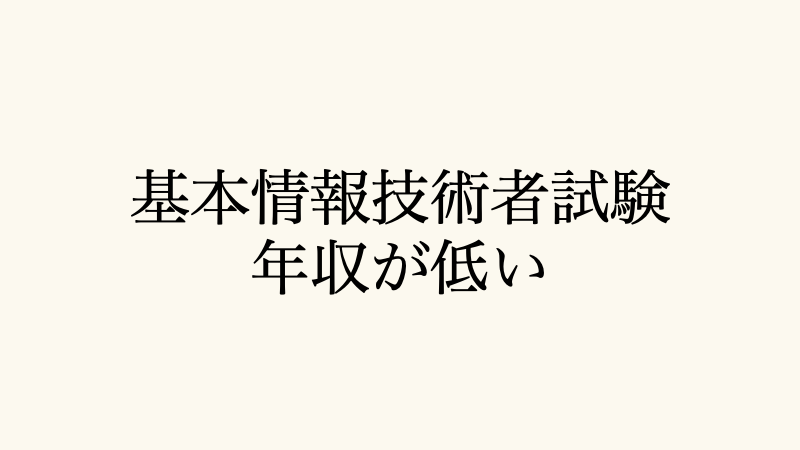



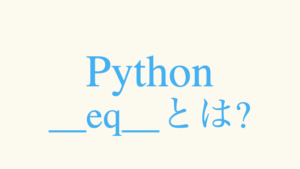
コメント